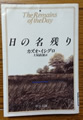愛なき世界
三浦しおんさんと言う人、いろんな事を探求される方だ。
男の祭りにスポットをあててみたり。広辞苑を作る人にスポットをあててみたり・・。
たぶん誰も書いていない分野を開拓してみたい、知ってみたい好奇心に溢れていらっしゃるのだろう。
今度はとうとう植物だ。
植物にまで手を拡げて来たか。
正確には植物を研究する研究者にスポットをあてたわけだが、植物の研究などと言う地味な分野、果たして読み物になるのだろうか、などと余計な心配は杞憂に終わる。
人物を描写が絶妙な人なので、扱う題材が珍しかろうが、地味だろうが、なんでも楽しく読ませて下さる。
主人公はおそらく東大と思われる大学のすぐ近くにある洋食屋で働く青年。
彼が一目惚れをしてしまうのがその大学の植物学の博士課程で研究する女性。
その女性の研究対象が「シロイヌナズナ」という植物。
葉っぱはどうして一定の大きさ以上にならないのだろう。
そんなことを疑問に思う人はそうそういないだろうが、そういう事を疑問に思う人たちがいるから、自然界の謎が一つ一つ解き明かされて行くのだろう。
恋愛の話では男が女の気持ちに鈍感、というのが通例だと思うが、この研究者の場合は逆だ。彼女は洋食屋のお兄ちゃんのことは嫌いではない、むしろ好きな方だと思うが、彼女の方が男の気持ちに鈍感なのが面白い。
むしろ、それだけに彼の方も立ち直りが早い。
今、ちまたのニュースで聞かない日はない「PCR検査」。
この本には何度も「PCR検査」という言葉が登場する。
変種の遺伝子を配合させてさらにその種どうしを配合させてさらに・・と途轍もない労力をかけて最後の最後に使うのが、そのPCR検査。
今、ニュースで聞くPCR検査とおそらく同じものなのだろうと思う。
そんな研究者が最終手段で使うような検査を毎日毎日、全員やれだのとニュースで流れているのか。
こういう研究者たちはどんな思いでそのニュースを聞いているのだろう。
ちょっと、気になってしまった。