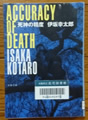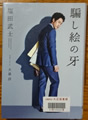死神の精度
主人公はなんと死神。
死神は調査対象者を指定され、一週間その対象者の行動を観察。
彼らには「見送り」にする(生かしておく)か、「可」とする(そのまま死を向かえる)かの判断をする権限がある。
そもそも対象者として選ばれる基準も不明なら、かれらが観察することで生かしておくべきかどうかの判断材料があるとは思えないしそもそも判断基準など存在しそうにないのだが、主人公の死神氏は仕事を怠らない。
真面目なのである。
とはいえ、きまぐれで、というより自分のほとんど趣味で「見送り」の決裁をすることもある。
この世に何十億の人が居ようが、どの人間にも共通していることが一つある。
人は必ず死ぬ、ということ。
普段、健康な時は忘れているだけで、いつかは必ず死ぬ。
死神はごくごく当たり前の事を言っているだけでも、それを聞いたら、皆、ぎょっとするか、んなわけねーだろーが!と怒ったりするものだ。
この話の上でだけだが、唯一、絶対に死なない期間がある。
死神が調査(観察?)をしている一週間だ。
その間、その対象者はどれだけ無茶なことをやろうと、死神が判定する一週間後にならない限りは死なない。
二篇目に出て来る昔気質のヤクザ。
今どきの体質の身内からも売られる格好となるが、彼は抗争相手にひるまず単独でも立ち向かおうとする。
彼などはその調査中につき死なない典型だろう。
どれだけ無茶なことをしてもその一週間の審判の日を迎えていないということは、まだ寿命かあるのだ。
絶対に死なない。
雪の中の宿泊施設に集まった客たちが、一人一人謎の死を遂げていく。
推理小説になりがちな展開に死神が絡む。
一篇一篇は独立していているのだが、それぞれの時代が違う。
別の一篇では若い人間として登場した人物が別の一篇での登場人物になっていたりして別々の話が実は繋がっていたりするあたりは、やはり伊坂氏らしい。
死神というと響きが悪いが、かなりいいやつだ。
とはいえ彼は人からどう思われるなど、どうでもいいのだが・・。
人が生きていようが、死んでいようがさえどうでもいい。
ただ、音楽が聞ければそれでいい。
発言が突拍子もないのだが、案外それは日本語特有の表現の難しさが原因だったりする。
もう何百年も前から何度も来ているなら、いい加減、言い回しぐらい理解しろよ、と言いたくなるが、それは仕方がない。
彼には興味がないんだから。
真面目、強い、渋滞が大嫌いで、音楽が大好き。非常にユーモラスで、人に案外好かれる。
こんな死神を描けるのは伊坂氏ならではだろう。