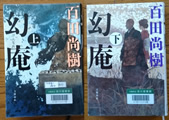プーチン 内政的考察
プーチンが最初に大統領に就任したのが、2000年。間にメドベージェフを傀儡として立てた時を挟むが、まる17年間、ロシアのトップに君臨してきた。
アメリカの大統領が任期4年再選でMAX8年の倍以上。
日本のどこかの地方自治体ならともかく、世界のトップリーダーの中でこれだけ長期に渡って政権を維持している人はおそらくいない。
著者の木村先生は2018年の大統領選もプーチンで確定とまで断言しておられる。
となると25年・四半世紀という長きに亘っての政権維持となる。
25年がどれだけ長いか。
幕末にペリー来航から江戸時代が終わり新政府が出来てその新政府を作った中心人物(木戸・西郷・大久保ら)が全員死に絶えるまでの間が25年なのだ。
その間にどれだけのことがあったか。
四半世紀というのは島国日本でさえそれだけの歳月だ。ロシアという広大な国ではなおの事だろう。
2000年からの2期をプーチンPART1だとすると、このPART1は大成功。
旧ソ連邦参加の国が次々に独立し、ソビエト連邦そのものも崩壊。そして何百人という貧困層の出現。
そんな中で就任したプーチンに求められたのはグラスノスチ(情報公開)の延長でも無ければ、ペレストロイカ(政治改革)の延長でも無かった。
強いロシアの復活と国民を貧困から脱却させること。
この貧困からの脱却という点では、プーチン期に入って原油価格が高騰したこともあり、国民への期待には見事にこたえた格好だ。
PART1の幸運な大成功に比べると、プーチンPART2は問題山積み。
原油価格の暴落、ウクライナ危機にてEU諸国よりの経済制裁、原油で稼いでいる時に産業育成をしてこなかったつけが廻って来て、天然資源輸出に変わる新たな産業が何も育って来ていない。
日本の1/4以下のGDPでありながら、100万人とも言われる軍隊を養っていかなければならない。(ちなみに日本の自衛隊は23万人)
どれだけ大変なかじ取りか。
それでも大半のロシア国民はクリミア併合、ウクライナ対応を指示しているという。
だが、現在のロシアでいうところの支持率などというものがいかにあてにならないか、木村先生は教えてくれる。
メディアというメディアにはほとんど国の資本が入る。
外国資本の入ったメディアは許されない。
そして、支持率の調査にしたって、無作為に街中で声をかけたわじゃじゃない。
自宅にかかってきた電話に対して答えなければならないのだ。相手はこちらの電話番号を知っている、となれば下手な受け答えは出来ない。
須らく、指示する、と言っておいた方が無難に決まっている。
そんな支持率の数字、どれだけあてになるのか。
選挙制度も度々手を入れて来ている。
反対勢力が育とうにもその芽がどんどん事前に摘まれて行く。
何より、ジャーナリストの不審死者数が異様に多い。
プーチンが政権を取って依頼、プーチンに好意的な記事を書かなかった側のジャーナリストが年間平均17名もの不審死で亡くなっているという。中には明らかな暗殺もある。
それはプーチンが指示をしたのか、プーチンの気持ちをおもんばかった旧KGB系の連中が勝手に動いたのかはわからない。
それでも一人の政権の間に300名弱のジャーナリストが命を絶たれているというのは異常だろう。
明らかに民主主義ではない国、言論が自由では無い国ならば殺される前に発言しないし、その兆候があれば拘束されるだろう。
表向きは民主主義国家で、言論自由国家でありつつも実体は乖離していく。
木村先生が言う通り、プーチンが次も大統領で決定なら、プーチンPART3は更に厳しいかじ取りが迫られるのではないだろうか。