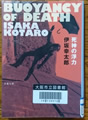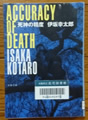火星に住むつもりかい
テロ撲滅を目的に作られた「平和警察」と言う組織。
本来は海外のテロ組織のメンバを確保する事が目的で作られたのだろうが、お題目と運用がかけ離れてしまうこと、多々あるものだ。
交通事故を減らす事が目的の取り締まりのはずが、いつの間にか交通課警察のの点数稼ぎのためとしか思えないようなことだってある。
でも必ず言われるだも交通事故は減ったでしょ。
ただこの「平和警察」は次元が違う。
一般市民が嫌いなやつを嵌めてやろうと思っただけで、即機能してしまう。
通報一つでますは勾留される。
自白を強要されるような拷問を受け、自白させられると今度は一般市民を集めた場所でギロチンでの公開処刑。
容疑はなんだったのか。
テロの一味だと思ったのなら、そこで処刑してしまっては意味がないだろう。
もはやそんな普通が許される状態からどんどんかけ離れて行く。
しかし何故歯止めが効かないのか。
だって犯罪件数は減ったでしょ。
それが推進派の言い分だ。
かつてアメリカの9.11テロの後、時の米政府はこれはテロとの戦いだと対テロ宣戦布告をし、怪しいと目される人物と関わった人さらにその関わった人に関わった人と次から次へと監視の網を広げて行く。
これは後にアメリカから亡命したスノーデンの告発によってもそれがプログラムによってかなり大規模にしかも世界に網を張った状態で行われていたことが明らかになって行くのだが、そんな監視社会を「平和警察」は作ろうとしたのか。
いや、もっとひどい。
監視によって容疑者となったなら、まだ容疑者としての根拠があるが、ここに出て来る「平和警察」は何でもやりたい放題。
自分の気分で捕まえることだって処刑まで持って行くことだって出来てしまう。
これに立ち向かうのが黒づくめの謎の人物。
その捜査協力に東京からやって来た真壁という捜査官。
結構立場が上なんだろう。結構「平和警察」のことをボロカスに言っても平気な立場なんだから。
いいなぁ、この人のキャラ。
話しの流れなんてお構いなしで虫の生態なんぞを語り始めてみたり、謎の人物をたぶん「正義の味方」と名付けたのも彼。
この小説、ジョージオーウェルの世界と比較されるんだろうな、と読みながら思ったが、
案外この平和警察に捕縛された段階で、メディアからも一斉に袋叩き。やがては公開処刑という一連、ネット世界での炎上、袋叩きの方が似ているところがあるような気がしないでもない。
正義の味方はそこにも出て来てくれるのかなぁ。