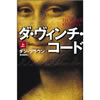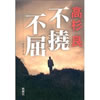マークスの山
行きつけの本屋で「李歐」と「マークスの山」が平積みにされていたので、何も考えずにまず購入してしまった。
購入した後で高村薫、高村薫、高村薫、高村薫・・どこかで聞いた覚えがあるな・・そうだ、レディジョーカーの作者では無いか。
あの「グリコ森永事件」を題材にほぼこれが真相に近いのでは無いかと思われる様な物語を書いた人だ。
「グリコ森永事件」と言うともうはるか前の事の様であるが、あの事件は地域性も身近であり、「けいさつのあほどもへ」で始まる挑発的な挑戦状が新聞トップを飾っていたのも印象に残っている。
あの事件を書いた高村薫の本か。と李歐をまず読破。
新しい形の美しく壮大な青春の物語だのなんだのっていう歯の浮いた様な誉め言葉が帯に書いてあったっけ。
そんなたいそうな、というのが実感。この本がそもそも書かれたのは大分以前であろうから、その頃にしてみれば現在頻繁に発生している中国人犯罪を予見していたと言う事だろうか。
出張など長旅のお供には丁度いい本かもしれませんよ。
さて、いきおいで買ったもう一つの「マークスの山」。
この本で面白いところは、警視庁という組織の有りようが良くわかるところだろうか。
同じ捜査一課でも係りが違えば、他所の組織となって情報のやり取りすらスムーズには行われない。
東京で発生した連続殺人。その関係者を調べて行くと、必ずや行き当たるのが某大学登山部の同期生。
各々が地位ある立場となった人達だ。またその人達も次々と死んで行く。
捜査に乗り出した刑事は上からの圧力との戦いをしなければならない。
犯人は自らをマークスと呼ぶ青年。
二重人格者なのか多重人格者なのか、それとも大人しい性格の時は、単に芝居をしていただけなのか、ついに最後までわからない。
結局、一連の事件の背後には十数年前、その地位ある人達まだ学生だった時代に遡る。
詳細は書かないが、事件の解明に至るのは、同期の登山部の卒業生の医者(病院長だったか)が、書き残した遺書である。
なんともはた迷惑な遺書を残したものだ。
同じ同期の登山部仲間と南アルプスへ登山した際に、同行した一人を不幸にも死に至らしめてしまった事について、遺書の中で詫びたいというのなら、その人に対する哀悼の念だけを書けば良いだろうし仲間の事も書く必要は無いだろう。
ところがこの医者、自分が癌で先が無いからと遺書を書くのはいいが、あまりにも饒舌なのである。
仲間の学生時代の秘密、裏口入学で入った事やら、交通事故のもみ消しが有った事やら、墓場まで持って行けばいい様な事を全て暴露しているのだ。全く遺書としては書く必要の無い事を書いている。
そういう内容の事を書き残す事で、それが少しでも漏れれば、仲間であったかつての同級生にどれだけ迷惑がかかるか、想像すればわかるだろうに。またそんなものどこから漏れるか知れたものじゃない。
自分の死を直前にしての仲間への裏切りであり、最後っ屁としか思えない。
この本上下巻の長編なのだが、作者は刑事に突き止めさせる努力を怠ってしまったのだろうか。
捜査会議の描写やら、キャリア対ノンキャリ。各捜査班同士の対立など、現実的に見える箇所がふんだんにあっていろいろな圧力の中苦労して捜査する過程を散々書いておきながら、この様な非現実的で一足飛びで真相解明の遺書の登場。
そして、犯人の青年についても記憶障害という病気でありながら、綿密な計画を立てて実行して行く過程についても結局非現実的のまま終ってしまった。
やっぱり、現実にあった事件をモチーフとしないとレディジョーカーの様な作品は生まれないのかなぁ。