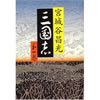チャイナ・レイク
アメリカの一地方での新興のカルト教団をめぐる話である。
日本と欧米では宗教に対する寛容さはかなり違いがあるだろう。
日本人はその人が信じている宗教の内容、教義というのか?に対してまでそうそう口出しをしたりはしない。
ただ、自分が入信を薦められたら、お断りをするだけで、滅多に馬鹿にしてみたり、などはしない。
それは寛容というよりも怖いからなのかもしれないが・・。
いずれにしても春・夏の甲子園にでも過去結構な数の宗教の関係の学校が出場して来ているはずだが、それに違和感を感じる人は少ない。
欧米ではキリスト教以外は異教であるから、どうしても新興の教団と言ったってキリスト教から大きく離れるわけには行かないのかもしれない。
大きく離れるどころかもっと原理主義的なまでに熱烈なのが新興カルトとして度々登場する。
結構平気でその人達の目の前で、教義をからかってみたり、ジョークにしてみたり出来てしまうのは国民性の違いなのだろうか。
日本でも例外はもちろんある。
ハルマゲドンだったか、終末論を煽り、実際に予言が当たらないとなると、自らサティアンなるところに信者が籠もって化学兵器を製造し、東京の地下鉄にサリンという猛毒をばら撒いたあの教団である。
この小説に登場する教団も終末思想を唱え、聖書を引用しながら、自らその終末を起そうとする。
日本のあの事件をかなり参考にされたのではないだろうか。
ここではサリンでは無く、狂犬病ウィルスを用いようとする。
そのメリットは潜伏期間が永いため、犯人が特定されづらいこと。非常に致死率が高いこと・・などだが、読みすすめると結局なんでも良かったんじゃないのか、とも思える。
この教団、死者を冒涜し死者に鞭打つ。
エイズで亡くなった人の葬式に大勢でプラカードを持って現われ、その死を冒涜する。
どこまでされたら、いくら信じるのは勝手と言いながらも、その教義に反論したくもなるだろう。
「チャイナ・レイク」という地名は実在する。
そしてそこが航空開発基地であることもどうやら実際の話らしい。
そのチャイナ・レイクともう一つの舞台となるサンタ・バーバラももちろん実在する地名である。
だから信憑性があるか、と言えばそれはどうだろうか。
誰だってまともな人間ならちょっと取り合えないほどにその教義はボロボロでどうしようもなく薄っぺらい。
その教団という恐ろしい組織に対して立ち向かうのが弁護士でもありSF作家でもある主人公の女性。
この女性の勇気は凄まじい。
ただ少しだけ残念なのは、その恐怖の教団そのものへ妄信する信者達の圧迫感というか、集団の怖さというものがあまり伝わって来ないところだろうか。
小説の読みやすさから言えば登場人物をあまり多くしてしまうと読みづらいということを意識してなにか、何か事がある毎に登場する教団側の人間はほんの数人、毎度おなじみの顔なのである。
しまいには最初から数人しかしなかったのではないか、とすら思えてしまうほどに。
この作者、アメリカ人でありながらなかなかアメリカでは出版の機会に恵まれず、ずっとイギリスで出版してきたのだいう。
運よくアメリカで認められて出版したのがこの2009年の今年。
で、いきなりアメリカ探偵作家クラブのエドガー賞の最優秀ペイパーバック賞を受賞したのだという。
探偵作家クラブの賞というと探偵物のイメージを想像されるだろうが、決して探偵者ではない。
なかなか読み答えがあって読み出したらやめられない本であることは確かだろう。