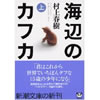歴史を遡るだとか、時空を超える話、いわゆるタイムトラベルをしてしまう話はいくらでもある。
望んで行く話、偶然に行ってしまう話。
行った先の歴史を変えてしまう話。
絶対に歴史を変えてはならない、と眺めている様な話。
この「蒲生邸事件」という話もまさにタイムトラルの話。
ただ、他のタイムトラルの話と決定的に違う点がいくつかある。
一つはそのタイムトラベラーの能力を持った人間は一様に皆、暗く、陰気で顔を見たら、ガラスをギーっと擦る音を聞いた時に似た嫌な気分になってしまう。
彼らは友達はもとより、親兄弟の誰からも無視され続ける存在。
また、それだけ存在感が無いのだ。
こんなタイムトラベラーは他の話ではあまりお目にかかれない。
その暗さ、存在感の無さの理由は、他の時代へ行ってもその存在感の無さ故に誰からも気に留められることがないからだという。
それでも彼らはその能力を発揮しようと、歴史を変えようとするのだが、歴史というものの流れは決して変わる事がないのだという。
あの忌まわしい事故、日航ジャンボ旅客機の墜落をなんとか未然に防ごうと、飛行機に爆弾を仕掛けたと電話して無理矢理欠航させ、その飛行機は墜落を免れたとしても、その翌日か翌々日に別のジャンボ機が墜落する。
そうして、歴史はちゃんと帳尻を合わせるのだという。
日航ジャンボ機はあの時期に一機、墜落をしなければならない宿命があったのだという。あの山崎豊子の「沈まぬ太陽」がその後に明らかにした様な、日航そのものの安全管理をないがしろにした会社の姿勢はそういう形で何か事件にならなければ、改まらなかった、ということなのだろう。
だから、どのジャンボ機を救おうと、別のジャンボ機が必ず墜落する。
ということは、歴史は必然、という事なのだろうか。
ということは大化の改新の時、蘇我入鹿に事前に事件の事を告げていてもやはりどこかで蘇我蝦夷・入鹿親子は殺害されたということなのだろう。
現天皇を廃して蘇我天皇が誕生しつつある事態を撲滅させるのが歴史の望んだ結果だということか。
本能寺の変直前にタイムトラベルをして明智光秀を拉致監禁してしまったとしても、他の誰かが織田信長を倒すのだろうか。
自らを王と称し、寺院を焼き討ちにする様な存在は誰かが討つのが歴史の必然だということか。
ただ、本能寺の変の際には織田信長を討てるのは明智光秀しかいなかった。他の武将は皆遠征ではるか遠くまで行っていたはずである。
それでもその明智を拉致しても織田は誰に討たれるのだろう。明智の部下だろうか。
某日本放送協会でやっている「その時歴史が動いた」という番組がある。
まさしくその瞬間の行動が、その瞬間の判断の左右によって歴史はこんなに動いたのだ、という紹介話である。
でも、歴史が必然なら、その瞬間の判断を右から左へ変えてあげたとしても結果は同じだったということになるのだろう。
バック・トゥ・ザ・フューチャーとは対極にあるタイムトラベル話である。
さて、時代は二・二六事変である。
ここに登場するタイムトラベラーは他のどの時代への選択肢もあっただろうにこともあろうか、二・二六事変の直前からを自分の永住の地と定めた。
だんだんと日本全土に暗い影がさして来た頃なのじゃないのか。
それは戦後の人間が勝手にそう思っているだけで存外に今よりも住みやすい時代だったのかもしれない。
それでもその数年後には戦争へと突入して、最後は散々空爆されて、戦後は食うものもない時代へと流れていくわけだから、最終的には住みやすい時代であるはずがない。
作者は蒲生大将(架空)が未来を覗き見てしまったがために変節をし、未来の人からあの時代にそれだけ先を見通していた人がいたのか、と後世に名を残し、子孫を助けようとする様な人には歴史に不誠実な人としてばっさり切り捨てる。
東条英機の様に最後まで悪者で通して、戦犯となったの方が歴史に誠実、正直であったと寧ろ評価が高い。
では、二・二六の時代へ移り住もうとしているこのタイムトラベラーはどうなのだろう。赤紙で戦地へ引っ張られてしまえばどうしようもないが、引っ張られなかったとしたら・・。
東京への大空襲のことも知っているだろうし、長崎、広島へ原爆が投下されることも知っていれば、8月15日に玉音放送がある事も知っている。
戦後に起きること、朝鮮動乱のこともその後にどんな産業が伸びるのかも、ケネディの暗殺もアメリカの有人宇宙船月着陸も、東京オリンピックも大阪万博も・・・この歴史に影響を与えることをやめた人がそれを知ったからといって、先見の明を発揮したり、株でボロ儲けすることもないだろうが、戦争を生き抜いとしたらその先の人生は果たして面白かっただろうか。
未来は自らの手で作るもの、と言うが、彼は決して未来は作れない。
何故なら歴史に縛られているから。
彼はだけではないのかもしれない。
歴史には流れというものがあり、その流れには決して逆らえないのであるというように過去から今日に至る歴史が必然なのだとしたら、未来だって同じではないのか・・・必然。
未来は自らの手で作るものなのではなく未来は定められた必然のルールどおりに進んで行く?
この本にはそのような意図はないのはわかっている。
昭和初期の日本でしか存在し得ないような優しい温もりのある女中のふき。
ふきと主人公とのロマンスなどがあれば、随分違う感想をもつのだろうが、二・二六事変に訳もわからず参加した兵士への「原隊へ戻れ」の号令。
「原隊へ戻れ」をふきから復唱され、戻るべきところへ戻る主人公。
それだけでもふきという女性の優しさは伝わってくる。
感想としてはそういう締めが望ましいのだろうが、蛇足は書かずにはいられない。
歴史の落ち着く先が決まっている、という宮部流歴史必然説に沿えば、未来は自らの手で作るものなのではなく未来は定められた必然のルールどおりに進んで行く。
では、未来を、この地球の未来を変えようとする人々の努力はいかに。
地球温暖化は続き、ツバルは沈み、北極から氷がなくなっていくのは歴史の必然?
洞爺湖サミットにても結局、2050年と彼らの次々世代に対しての約束事でさえ、中国、インドからの前向きな発言を日本国首相は得られなかった。
これは宮部流必然説でもなんでもなく、まさに我々の目の間の現実そのものなのだ。
歴史のこの未来の必然の行き先はこのまま推移すればもうほとんど見えていると言っても過言ではないだろう。
最後に、それでも我々には我々の子・孫の世代のためにもその必然の未来を変えるための努力をする義務があるはずだとこころから思う。