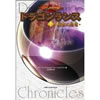氷点
私の枕もとにはいつも何冊かの未読本が積まれている。
とっとと片付けてしまおうと思うのだが、新しい本を購入するペースの方が早く、以前からずっと積まれたままの本は相変わらず積まれて下に埋もれたまま新刊の方を先に読み始める。
三浦綾子という作家、以前からクリスチャンであるという事は知っていた。
この『氷点』を購入したのもだいぶ以前の事である。
ひょっとして大昔に読んだのではなかったか、と思いつつも何故か本屋の書棚から引っ張り出して購入してそのままだった。
昨年末にこの『氷点』のドラマ化をしたものが放映される、というので録画予約をして、本を読むより先に見てしまった。ドラマを観てやはり昔に読んだものではない事がはっきりした。
録画の時間を間違えたので全ては観られなかったが大筋は理解した。理解してそしてついバカ笑いをしてしまった。
幼い娘が殺害された病院長が、殺害した犯人の娘を養女として引き取り、その養女を育てさせる事で娘が殺害された時に男と逢引をしていた妻への復讐をしようとする。
いずれその事実を知った妻が今度はその養女を苛める。
学芸会の時に一人だけ衣装を揃えてやらなかったり、給食費を渡してやらなかったり。
卒業式の答辞を読むにあたってその答辞の原稿を抜き取ってしまったり・・
いったいどこまでいくんだ!あぁー!って、その滑稽さに笑いまくってしまったのだった。
だからなおさら、本への手は伸びなかったのだが、何かの拍子で本の山が崩れ、現れ出でたるのがこの『氷点』だった。まるで読んでちょうだい、とでも言う様に。
ドラマで大筋を知ってしまっているだけに読むスピードは速かった。
しかし読み始めてみるとどうだろう。ドラマを観た時に感じた滑稽さなどは微塵も無い。
なんともシリアスな話なのである。
このシリアスさを理解するには昭和20年代という時代背景を考慮に入れなければ成り立たないであろう。
近年はもっぱらレトロブーム。昭和の時代は良かった。あの頃は夢があった・・と。
現代日本人が失った何かを持っていた時代。
そしてその何かの中には「恥」という概念も含まれているのだろう。
そしてその何かの中には「寡黙」というものも含まれているのかもしれない。
妻が浮気をしているかもしれないというのにその事を妻に直接尋ねるも出来ないこの啓造という病院長。
この平成の時代にあっては妻が浮気をしようがしまいがどうでも良いと思う夫はざらにいるだろう。
逆に気になる人は夫婦喧嘩をしてでも問い詰めるか。
今を時代背景として考えると啓造というキャラクターは成り立たない。
だからこそ余計に現代人が演じるドラマなどで観てしまうとその行為は滑稽を通り越して異常としか言い様が無い。
いや昭和20年代であったとしても異常である事には違いは無いのだろうが、そういう事を問い詰める事そのものに対する卑しさの様な気分的なものを残していた時代なのかもしれない。
それにしても学生時代からの恩師の教えである「汝の敵を愛せよ」を実践する、という言葉と裏腹に自分の妻を許すどころか一番陰険な復讐方法を考え、それを実践してしまう感覚はどうだろう。
いずれにしろ「恥の美徳」や「寡黙の美」を日本人がまだ持っていた時代は同時に己の美徳からはずれる者に対して陰険で暗い粘着性の様なものも前時代から引き継いでいた時代なのかもしれない。
この本が出版と同時にベストセラーとなったという事実はそういう時代背景の引きずりがあったからではないか、などと思ってしまうのである。
それにしてもこの養女となった陽子の明るさ、強さ、性格の良さはいったいなんなんだ。
小学校に入った頃に隣に座っている子はどんな子?前の子は?後ろの子は?と聞かれる場面があるが、どの子に対してもいいところを見つけて褒める。
人を悪し様に言う事を決してしない。
真実を知った母親からどんな目に合おうと告げ口をしない。
常に明るく明るく振る舞い、逆境を逆境と思わない強さを持っている。
この子こそ、神の子なのでは無いのか。
子供というもの、わがままなのが当たり前な生き物である。
子供の心は清く正直だ、などと言う勘違いを耳にする事があるが、子供だって嫉妬心もあれば嘘もつく。正直だというのはその嘘のつき方が下手だというだけだろう。
陽子はわがままという一般的な子供が持っている特性を持たない。
この養父養母は「血」というものへのこだわりが強いが、子供の育つ後天的要素についてはどうなのだろう。
子は親の背を見て育つと言われるが、給食費をくれない母親に文句を言う代わりに牛乳配達を始めるという発想はまさか「血」ゆえではあるまい。この両親のどこからそんな要素が受け継がれたのか。
幼い頃より父の膝に座る事さえなかった子供がここまで明るく他人に対して優しい性格を持ち得るのか。
今のご時世、親は子供から無視をされるご時世。
子供にとって父親は外で金さえ稼いで来てくれればそれで良く、ウザくて近寄ればオヤジ臭さが移りそうで、近寄るのも話をするのも嫌。
また母親は賄い婦であり、掃除婦であり、買い物に走らされる雑用一切をすれば良い家政婦の様な存在。
少子化のこのご時世の中では子供はこわれものの宝物の様に育てられ、家の中で一番偉そうにしているのが子供。
そんな家も多いのではないだろうか。
有り得ない様なありがたい「神の子」の様な子を授かりながらそれに気が付かない憐れな養父母の姿。
作家が描こうとしたのはクリスチャンならではの「許し」であり、生きている事そのものの「原罪」なのかもしれないが、読む側にしてみればどうしても平成のこの時代の現実を重ねて読んでしまう。
やはり平成のこのご時世に置き換えて考えて見る事そのものが滑稽な行為なのだろう。
なんとも言えない異質な気分が残る。やはり違和感はぬぐえない。