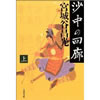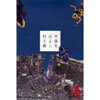沈黙の王
宮城谷続きになってしまった。
宮城谷氏の本と言えば、どうしても奇貨居くべし (春風篇)(火雲篇)(黄河篇)(飛翔篇)(天命篇)の全5巻、孟嘗君(全5巻)、香乱記 (全4巻)、楽毅(全4巻)、重耳 上中下巻、晏子 上中下巻・・・などの様に長編の大作を思い浮かべてしまう。
氏の本にはいつも泣かされる。感動の泣きと言う意味では無く、読み出したら途中でやめられないので睡眠時間が減ってしまい、これだけの大作ばかりとなるとほとんど寝る間が無い。
今回、紹介するのはいくつかある短編の中の一つ。
何故この短編を選んだのか、それまで文明をくつがえす様な発明、発見が描かれているからである。
「沈黙の王」は初めての文字というものを創造した経緯が描れてる。
商王朝の王子であった子昭は、王位を継ぐ立場にあったが、発声器官の疾患の為、満足に話す事が出来ない。
父であり王である小乙(商王朝21代目の王)は、子昭を追放せざるを得なくなる。
王の口からじかに命令を発せられない、という事は臣下にとっても王朝にとっても大問題だからである。
子昭はことばをさがす旅に出る訳だが、出発前に犬の血で作った小さな池に履を濡らす場面がある。
犬の嗅覚がすぐれているので、その血にも同じ働きがある、と考えられ、履に染みた血は地中の悪霊の臭いを嗅ぎ分け、足をかばってくれる、という現代で言えば迷信の様な事がこの時代の常識である。
宮城谷氏の本にはこの様な、読み飛ばしてしまいそうな箇所に満遍なくこの様な貴重な話が散りばめられているので要注意である。
王都を出て、荊棘の道を歩き、族に出会い、奴隷狩りに捕まるのだが、子昭に備わり始めた王としての威厳が常に子昭を助けてくれる。
王が死に、王都へ帰り22代目の王に即位する。
「子昭は史書では武丁と書かれる事が多い」と作者はここではじめてこの話は高宗武丁を描いたものだと知らされる。
なんとも意地が悪いのである。
「わしは言葉を得た。目にも見える言葉である。わしの言葉は万世の後にも滅びぬであろう」
「象(かたち)を森羅万象の中から抽き出せ」
こうして生まれたのが象形文字。(中華の場合は亀の甲羅や牛や鹿の骨に刻まれので甲骨文字とも呼ばれる)
白をどうやって象形するのか。永久不変の白は頭蓋骨。よって頭蓋骨を単純な線で描き、「白」という文字は生まれる。
森羅万象の中からかたちを作る、というのは途方も無い作業であっただろう。
「地中の火」
夏王朝(前述の商王朝よりも前の時代)の初期の天下の覇をめぐる権謀術数を描いていきながら、この作品では、弓矢が兵器として、初めて使用されるいきさつを教えてくれる。
中華では異民族や野蛮な族を蔑視して「夷」と呼び、中華から見れば日本も夷の一つであったわけだが、この夷という文字は大弓をつめた文字だと言われる。
その様に野蛮な未開人が使う道具としての弓を持って「弓矢で天下を制する事が出来る」と寒さく(「さく」はさんずいに足)は言う。
さながら、戦には不向きと言われた火縄の鉄砲を持って以降の戦は鉄砲無しでは成り立たない事を示した織田信長を連想してしまう。
「妖異記」と「豊饒の門」は、
周王朝(前述の商王朝よりも後の時代)の事実上の滅亡と春秋戦国時代の開始を描いている。
褒じ(じは女偏に以)という稀代の美女の妖気が歴史を動かす。
「鳳凰の冠」
これは短編というには少々長い。
春秋時代の晋の話である。
晋の公室の流れを汲みながらも地位に恵まれない羊舌氏の中にありながら、学問に励み、博識を認められ、太子の太傅(教育者)に任じられる叔向という人を描いている。
太子は彪と言い、後に即位して平公となる。
当時中華の覇を晋と争っていた楚の宰相をして「晋が覇者になるのも当然。叔向が補佐しているから」と言わしめるほど、叔向は平公の名補佐役となって行く。
この話、叔向という人の賢臣ぶりを描きつつ、賢妻、賢母とうたわれた叔向の母である叔姫との心の戦いをも描いている。
叔向をして母の様な人とだけは結婚したくない、と思わせるあたり賢母も行き過ぎれば、うるさい教育ママとなってしまう、という事であろうか。
叔向は母の最も嫌うタイプの女性である夏季の娘と結婚するのである。
時代の大きな流れに紛れてしまいそうだが、ここにもこの時代の風景を表す当時の常識というものが何気なくふれられている。
「婚礼というもの、けっして祝うべきもので無い」というのが当時の常識。
結婚は世代交代の象徴であり、来たるべき新世代を喜ぶよりも旧世代となって去らねばならぬ今の時を哀しむ気色が濃厚で、男は黒い礼服で新婦を迎える。今日の礼服はその名残りなのであろうか。
いずれも読み飛ばしてしまいそうな箇所にこそ、興味深い話がひょっこりひょっこりと出て来るのが宮城谷作品の面白さである。
今回紹介の本なら短編なので睡眠不足にもならずに済む。