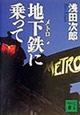てのひらの迷路
24のショートショート集。
ショートショートと言えば星新一があまりにも有名だが、この石田衣良氏のショート・ショートはSFでも未来ものでも宇宙ものでもホラーでもない。
石田衣良氏の実体験を元に書かれたものが大半である。
何気ないタクシーの運転手との会話。ただそれだけのショートショート。(タクシー)
目を閉じて正確に3分間を言い当てる。完璧なタイムキープを求められるアナウンサーの女性。(完璧な砂時計)
引きこもりを題材にした話。(銀紙の星)
実になんでもない話のようなのだが、何故か次は、次は、と次の短編を読みたくなってしまう、という不思議な本だ。
家の近くを散歩する。同じ様に散歩をしている、よくみかけるおばあさん。
おばあさんの話相手になりながら、散歩をする作者。
この何気ない短編からは作者の優しさ、心遣いというものが伝わって来る。(終わりのない散歩)
本に関する短編もいくつか載っている。
世界に一冊だけ自分のためだけにある本があるに違いない、と書棚一杯の蔵書を読んでは捨てて、という選別をしている老人。(書棚と旅する男)
希望を失いかけた人の前に表れる一冊の本。
その本にはまさに自分と同じ境遇の主人公が登場し、奮戦の上、その境遇を乗り切る。
希望を失いかけた人はその本を読んで希望を取り戻し、また別の人のためにその本を置いて行く。
これなどは、まさに世界に一冊だけ自分のためだけにある本をもじったファンタジーである。(旅する本)
石田衣良氏は就職活動などはしなかったらしい。
最初に仕事をしたのはフリーターで、特に人生に野望はも大きな目標も持たないが、好きなだけ本が読めて、音楽が聴けて、生活をする上での金さえ稼げれば、それだけで充分じゃないか、そんな人生観を若い頃には持っておられた。
あぁ、この人にとっては、人生勝ち組だの負け組だとなどという色分けなどちゃんちゃらおかしいのだろうな。いや少なくとも若い頃はそうだったに違いない。
ニートだから、フリーターだから、非正規雇用社員だから、などという劣等感を持つ人間など、この人の若い頃の人生観からすれば不思議で仕方なかったに違いない。
広告代理店に勤めてからも有名なコピーを作ることなど眼中にはない。
偉くもなりたくはないし、人並み以上に金を得ることにも興味はない。
仕事には100%の本気は出さず、適当に手を抜きながらも一応与えられた作業は人並みにこなす。
それでも平日に自由に外を散歩したり、たっぷり本を読む時間は確保する。
そんな生活で満足していた人。
それがなんの因果か、小説を書き始めてしまってからというもの、途端に締め切りに追われる多忙な人となった。
そんな作者としての苦労話なども短編になっている。
この短編を練るまでの作業がそのまま短編にもなっていたりもする。
作家になってからの取材話の短編有り。
いずれにしろ、あの「アキハバラ@DEEP」などを書いた作者の作品とは別の一面を存分にのぞかせてくれる本であることは間違いない。
この短編、最初から24作で終ることになっていたらしく最後の一つ前の短編は作者が最も力を注いだものかもしれない。
そんな力作は力作としてもちろんOKなのだが、どんな仕事であれ、達人の域というものがあり、その道の天才といえる人がいるのだ、ということを描いている「ウエイトレスの天才」のような小編が私は好きである。