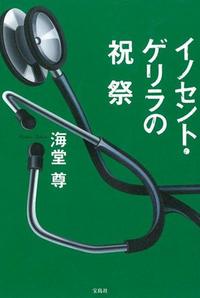文学少女と死にたがりの道化
「恥の多い生涯を送って来ました。」という出だしで始まる。
ご存知、太宰治の『人間失格』。
その人間失格をそのままモチーフにしてストーリーは進んで行く。
まるで、人間失格をそのままなぞらえるが如くに。
ここでは10年前の人間失格に染まりきった高校生と現時点の人間失格に染まりきった高校生が登場する。
そして人間失格の主人公そのままに道化に依って、朝から晩まで人間をあざむいているはずの自分の実態を見破られた人間を怖れる彼ら。
そう、人間失格の中でお道化で笑いをとっている最中、唯一「ワザワザ」とささやくあの同級生に出会った時の主人公さながらに。
この本、本の装丁から言えば、女子中学生ならまだしも、いい大人がちょっと人前で読むには憚られるような少女ものっぽい表紙なのだが、中を読み進んで行くうちに、あまりに太宰への造詣の深さに驚かされる。
主人公の先輩で自らを文学少女と名乗る文芸部の先輩が、羊よろしく、人の書いた文章を食事代わりに食べて行く、なんていうあたりはご愛嬌だろう。
肉筆のものが味があるなんて言って、書いては食べてしまっていては、この文芸部では一切作品は残っていかない。
そんなことよりもこの天野遠子という先輩文学少女が太宰の生き方共感者に投げつける言葉が素晴らしい。
太宰の作品を全部読み終えるまでは死んではダメ!
走れメロス その一番素晴らしいところはメロスが全裸で走っていたところである、と。なるほろ、原著を読んだ人しか知り得ないことだ。
メロスが全裸だったなんて。
「葉桜と魔笛」を読め! 優しさと希望と光がある!
「雪の夜の話」を読め!「皮膚と心」を読め! みんな優しくて純情で愛らしい!
「ろまん燈籠」を!「女生徒」を!
「おしゃれ童子」のユーモアを!
「如是我聞」で見せる太宰の人間臭さを!
「斜陽」の力強さを読め!
読め!読め!読め!読め!読め!と。
太宰は「人間失格」だけじゃない!
ハニカミ屋で優しい人たちがいっぱい登場するが強くもなれる人たちだ!
決して破滅型の作家じゃなかったことがよくわかるだろう・・・と。
なんとこの本はまさに太宰の入門本そのものだったんだ。
それにしても太宰という作家、平成のこの世においても何故こんなに人気があるのだろう。
昭和前期と平成という時代の違いは過去の歴史のどの時代の差より大きいに違いない。
それでも時代を超えて、感情移入させる力が太宰の作品にはあるのだろう。
かくいう私は「トカトントン」なんかが好きだったりします。