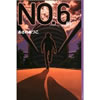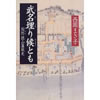香乱記
秦の末期から漢の時代の始まりまでという激動の時代が舞台である。
この時代の事を書いたもののなんと多い事だろう。
これまでで一番好きだったのは司馬遼太郎の『項羽と劉邦』だっただろうか。
経営者や管理職者向けのビジネス本にも多く取り上げられていた様に思える。
大抵の話が、秦の圧制に苦しんだ人々が陳勝・呉広というレジスタンスを迎え、歓喜し、やがて項羽・劉邦の新たな中華の項羽と劉邦という二大傑物を迎える。
その覇者争いを通して「勇猛果敢的経営」の破たん例 VS「適材適所的経営」の成功例などと取り上げられているのである。
司馬遼太郎はさすがにもっと極め細かく描いている。
だが、司馬遼太郎に限らず項羽と劉邦を扱っている本のほとんどは、
項羽は勇猛果敢で圧倒的な強さを持ち、若さを持ち、ある種の爽やかさを持つが、反面捕虜20万人を生き埋めにするなどの残虐さも兼ね備え持つ。
それに比べて、劉邦は戦下手で女ったらしでだらしが無い男でありながら、人の意見を聞く事に関しては天下一品で、人を重用する事に長けていたので、自らは何もしないでも側近に優秀な人材が集まり、到底勝てる相手では無かった項羽にも最終的には勝つ事が出来た。
と項羽の勇、武に対しての劉邦の徳の勝利だと両者を比肩する。
ところがこの「香乱記」においては項羽も劉邦もほとんどクズ扱いである。
この二人をこれほど悪し様に書いている本もそうそうないのではないか。
この違いはなんだろう。
項羽、劉邦とは別に田横という英傑を生み出し、それを主人公にして物語を書いたから、という理由ばかりでは無いだろう。
夏王朝から商の時代、周の時代、春秋戦国・・とずーっと長い長い目でこの古代中国史を俯瞰した宮城谷ならではの視点なのではないだろうか。
宮城谷の本に付き合えば付き合うほどに各時代の人徳の高い王や名宰相との出会いがある。
劉邦が徳のある人だって?笑わせるな!という気持ちが伝わって来そうである。
劉邦などと言う詐欺師には所詮、秦の真似事しか出来ないであろう。
項羽は戦は好きでもその後の国作りが行えるとは思えない。
秦滅亡から漢の樹立までの間に中華の人口は半減したと言う。
そこまでの代償を払って手に入れる新王朝が秦とどれだけ違うというのか。
秦という国に至っては、悉くが始皇帝の圧政・虐待政治という事が歴史上の常識と化しつつあるのかもしれないが、史上初の中央集権国家による法治国家を実現させた過去に例の無い国家である事も事実である。
過去を捨て去り、新たな国作りを行ったという意味では歴史上の大きな存在であろう。
但し過去を捨てると言っても焚書坑儒を行うに至っては後世の歴史家から見れば、研究材料を奪われたわけなので暴君と言われても仕方がないだろう。
兵馬俑で有名な始皇帝稜の建設、万里の長城の建設、阿房宮の建造・・と土木・建築に関しての規模はとてつもない。
歴史に名を残す建造物を残した時代というものにつきものなのはそこで働かされたであろう無辜の民による多大な労働力である。
やはりここでも圧政を布いたと言われても仕方が無いかもしれない。
趙高と共に地位を奪い取った二世皇帝に至ってはもう暴君を超えた単なる馬鹿扱い。
だが、実際にはどうだったのか。
秦は短命であった。秦の時代も漢の始まりも秦の後に出来た漢の時代に史書には記述されたであろう。
秦の法体系などをほとんど模倣したのではないかと言われる漢の誕生の正当性のためにも秦は酷い国でなければならず、
始皇帝は暴君でなければならず、
二世皇帝は馬鹿皇帝でなければならず、
項羽は20万の捕虜を生き埋めするほどに残虐でなければならず、
劉邦は人徳のある人でなければならなかった。
そういう側面が全くなかったなどとは到底思えない。
古代中華の頃の兵隊と言うもの、いとも容易く寝返る。
情勢の悪い軍隊ならさっさと戦いの場から逃げ出して、いつの間にか敵軍に入っていたり・・。
将棋というゲームの生まれる所以だろうか。さっきまで玉を守っていた飛車が敵のに取られるやいなやいきなり玉に王手なんだから。
そういう事が当たり前の時代の軍隊であり兵隊だ。項羽とてわかっているだろう。
敵の(秦の)将軍である章邯が降伏した段階で、章邯は項羽軍の将軍となった。
もれなく付いてくるはずの20万の章邯の兵士を何故生き埋めにする必要があったのか・・・・。
後の漢による情報操作で無いとすれば、全く意味不明である。
という様な事はこの「香乱記」の本題からはずれるので、ひとまずおいて置く。
宮城谷から見て、この時代を治める最高の人物は宮城谷そのものの描いたに田横だったのだろう。
田横という人は実在したかもしれないが、「香乱記」の中の田横は宮城谷の理想の人物として、描かれた人物像に違いない。
宮城谷本で言えば「孟嘗君」が一番近いか。
双方とも田氏である。孟嘗君は田文だった。
斉の国にはなんと田氏の多い事か、「香乱記」の中にも何人田氏が出て来ただろうか、味方ばかりで無く敵の中にも田氏が出て来る。
この本、出版前は新聞連載だったという。
連載で小刻みに読む読者は訳がわからなくならなかったのだろうか。
「香乱記」という本、他の宮城谷本を読破している量に比例して面白さが倍増するのではないかと思える。
秦の法治国家については商鞅を書いた箇所を読んでいた方がよりその法による政治の画期的さがわかるだろうし、呂不韋に助けられる前の人質であった少年時代の始皇帝の箇所を読んでいれば、一箇所に居を構えないなどの用心深さもその所以が見えて来る様な気がする。
また随所に引用される春秋以前の人の名。
これらは宮城谷本を読んでいる事を前提とでもしているかの様である。
とは言え、何事も第一歩が無ければ第二歩も無い。
宮城谷本はどこからはじめても面白い。
特に田横という爽やかな男を描いた「香乱記」は清々しい一冊である。