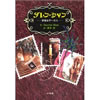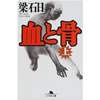ウエハースの椅子
おそらく、人に薦められでもしない限り、この本を読む事は無かったであろう。
この本を薦めてくれたのはこの本の中の登場人物と同世代の女性である。
私の知り合いまたは読む本に登場してくる女性になんとこの同年代の人の多い事か。
私はこの本についてはあまりコメントしたくは無い。
だが、読んだ以上はコメントせよ、との御達しなので致し方ない。
三十代後半の女性の視点ならではの描写がこれでもかこれでもか、と続いていく。
そのならではの描写には次第にうーんとうなってしまう。
別に物語なのではない。ストーリーすらない。
言わば今流行のブログのはしりの様な書き物か。
小学生時代の思い出も出て来る。
「なんでのこんな事をしなければならないのだろう」
同じ思いは実は私も感じたのである。
だが、私とこの登場人物との間には決定的な違いがある。
私は疑問に思った事はそのまま身近な大人(担任の教師だっただろうか)にぶつけたのである。
あれは何学期の事かは忘れてしまったが、とうとう堪忍袋の尾が切れた、と言わんばかりに険しい表情をしたその教師は教室の後方に座っていた私の所まで、早足で来るや否や、私に往復ピンタを喰らわせたのである。
その教師曰く、長年教師をやって来て、俺にピンタを叩かせたのはお前が二人目なのだそうだ。
一人目はどんな人だったのか、どんな事でピンタを喰らったのか、ピンタを喰らった直後であるにも関わらず、自分の好奇心にはやはり勝てない。そのまま質問してしまった。
その人が何年も前の小学生の女子であった事だけは聞き出せたが、残りの疑問には一切応えてはもらえなかった。
あの学校では5年の担任はそのままクラス替えも無く6年も担任する事になっていた。
私は6年生からは親の都合で転校してしまい、別の学校に移ったので、さぞかしその教師はほっとした事であろう。
話が思いっきり飛んでしまっている。
元へ戻そう。
この登場人物と同年代の三十八歳の女性であれば、多分に自分と重ねて見て、同じ思いを共有してしまう、とう事は無いだろうか。
この本の愛読者は反発するのであろうが、この本に共感を持った人を私は好きにはなれないだろう。
どうしてもポジティブにな気持ちを維持出来ないのではないだろうか。
あまりにネガティブなのである。
ウエハースの椅子では恋人は決して彼女を嫌いになったりはしないし、彼女も恋人にどっぷり浸かっている。
ただ、恋人がウエハースの椅子を自身の事として書いている姿を見た時、興ざめの様なものは起きないだろうか。
それでも彼は優しいので内面はどうであれ、外面は同じ様に優しいのであろう。