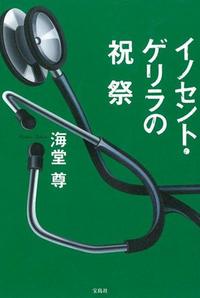イノセント・ゲリラの祝祭
ある新興宗教団体で起きた突然死という変死からこの物語は始まる。
実際は団体によるリンチ殺人事件だったのに、危うく急性心不全で片付けられようとしていた。
日本の死者解剖率は2%。
不審な死だと思われて、警察指定医にて出される死因はほとんど「心不全」。
「心不全」とは心臓が停止した状態を述べたに過ぎず、死因を特定するものではない。
死因が「心不全」とはつまり「死因不明」と言っているのと同じことなのだそうだ。
日本の死の9割以上が死因不明のまま放置されている。
先進国の中では稀有なことなのだそうだ。
それもこれも予算の段取りがつかないことがそもそもでありながら、誰も望んでいないメタボ対策みたいなものだけには巨額の予算が継ぎ込まれる。
この本はそんな事柄を背景として、厚労省の官僚を切って切って切りまくる。
故城山三郎に「官僚たちの夏」という高度成長期の通産省を描いた作品がある。
丁度現在ドラマ化され、放映もされていたかと思う。
その中で描かれる官僚達はまさしく日本の牽引役で、寝る間も惜しんで国家のために働く。
官僚たちもまさに戦後経済を引っ張っているのは俺たちなんだという意識があっただろう。
それでも何か違和感が残ることは確かである。
大臣が方向性を示したって、局長会議の方向性の方が優先される。
大臣は目指す方向に進むためには、局長たちに根まわしをしなければならない。
保護貿易か、貿易自由化か、省内は揺れるが、各々法案を作成するのは官僚たちだ。
法律の立案は立法府、即ち国会の仕事が三権分立の基本のはずが、いつの間にか官僚が立法することがもはや当たり前になってしまっているのだ。
戦後の復興をなし遂げようとしたこの「官僚たちの夏」の時代であれば官僚も省益のためよりも国益のために汗を流したのかもしれないが、現在は果たしてどうなんだろう。
会議のための会議、そんな無駄な会議というものが世の中のは多々ある。
それは何も官僚が主催する会議だけではないだろう。
あらかじめ結論も台本も決まっていながら、さながら会議で決まったような形式だけを重んじる会議。
そんな会議はこの日本の中に至る所で存在する。
台本からはずれた意見を言おうものなら次からその会議にも召集されなくなり、会議に参加すべき立場からも引きずり下ろされる。
この本の面白いのは、全てそういう会議の場のやり取りだけをメインに物語を成立させているところだろう。
特技がリスク回避、座右の銘が「無味無臭、無為徒食」。
ミスター厚労省と呼ばれるエリート官僚を大学教授が評した言葉。
部外者のみならず同僚の官僚自らがミスター厚労省にこう述べる。
「市民が必要とすることはせず、自分たちがやりたいことを優先する。やりたくない仕事は遅延させ、やりたい仕事にはあらゆる手立てを使ってブースターをかける。口先で指導、責任が降りかからない安全地帯で体制づくりに専念する」
それに対してミスター厚労省は 「そんなに誉めるな」 の切り返し。
なんとも笑えない現実が見えてくるようだ。
もちろん、官自らがそんな言葉を吐くのは小説ならではなのだろうが、なにやら本音を吐露されているような気がしてしまうのは自分だけだろうか。
この物語の流れは法医学が中心の解剖実施比率を高めることよりもエ-アイ:AI(オートプシー・イメージング)という呼称の画像診断を死後画像に用いることで死因不明放置の対処に、という方向性なのだが、根底は官僚批判そのもの。
上に書いた以外にも官僚自身の口から冗談まじりに官僚批判を山ほどさせている。
それが、はたまた正鵠を得ているように思えてしまうところが悲しい。
具体的な省庁名を出してでは稀有な本かもしれない。
今や官僚批判が世論の趨勢になりつつある。
この選挙期間中も各党ともそれを謳い文句にはしながらも、はてさてどうなんだろう。
小さい政府、大いに結構。
しかしながら、各党の政策実現には小さな政府どころか寧ろ大きな政府が必要となるのでは?と思えてしまう。
官僚からの脱皮を!と訴えながらも果たして可能なのか。
この本から汲み取れるような数々の無駄や欺瞞が廃せるなら大いに廃して欲しいものである。
でも逆に「官僚たちの夏」にあるように、事実上この国を動かしているのが官僚ならば、あまりの官僚批判の中で彼らのモチベーションがどうなってしまうのか、も大いに気になってしまう。
9月以降、この国はいったいどこへ向かっているのだろう。