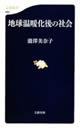地球温暖化後の社会
この著者の書き進め方、非常に好感が持てます。
温暖化だ!温暖化だ!とエキセントリックに騒ぎ立てているるのでは無く、誠に冷静な目で事実を分析しようとしていらっしゃる。
「うちエコ」という言葉をご存知でしょうか。
・車の運転で発進時にふんわりとアクセルを踏む・・207g
・ホットカーペットの設定温度を「強」から「中」へ・・193g
・自動車の代わりに自転車を使う・・180g
・エアコンの冷房を22℃から20℃に・・96g
・エアコンの暖房を26℃から28℃に・・83g
・シャワーの使用時間を1分減らす・・74g
・主電源をこまめに切って、待機電力を50%削減する・・65g
・冷蔵庫の設定を「強」から「中」へ・・64g
・車を運転する時1日5分のアイドリングストップを・・63g
XXgは二酸化炭素の削減量の目安。
などなどの個人レベルもしくは各家庭レベルで出来るエコ活動を「うちエコ」と呼ぶそうです。
上記の様な「うちエコ」を筆者は紹介しながらも、個人で出来るレベルの削減効果のMAXは17%でしかない、と述べ、「うちエコ」を最大限行ったところで根本的な解決には程遠いともおっしゃる。
但し、そういう意識を持つ事は大切なのだ、と。
アメリカの人、人にもよりますが、あのとんでもない浪費癖、エネルギーの無駄使い癖にはエコなど意識したことのない日本人でも驚くという話を良く聞きます。
日本人にはエネルギーの無駄使いを無くそうとする癖が元来あるように思えてなりません。
根本的な解決には程遠いと言いながらもその押しつけがましくない表現で伝えられるので、読む側は元々そういう意識が潜在的にあるだけに逆に「うちエコ」を意識してしまう。
この筆者にはそういう伝達力の巧みさを感じます。悪い意味では無く。
また、ゴミの分別やリサイクルについてもリサイクルを行う事で余分に化石燃料エネルギーを消費する様なリサイクルならやらない方がマシ、と述べる。
まさに当たり前のことなのですが、世の中なかなか当たり前が当たり前じゃないことしばしばです。
序章で温暖化に伴って発生するであろう異常気象などを列挙しておられるので、あぁこの方も環境オタクなのか?と思ったのですが、どっこいそうじゃなかった。
もちろん、環境を大切にする気持ちは同じでも、ものの見方が非常に冷静なのです。
二酸化炭素の増加と温暖化の関連性についての科学的根拠に否を唱える論に対しても敢えて反論をされない。
それでも歴史的背景から見て、産業革命以降に、更に第二次大戦後の石油エネルギー全盛時代に、さらにここ10年で温暖化が急速に進んで来た、という事実を淡々と述べられます。
筆者は既に温暖化がかなり進行していることを認識されています。
二酸化炭素の排出量を現在時点で西暦2000年レベルまで戻したところで、温暖化そのものが即座にストップするかと言うと、この先20年は続いてしまうのだそうです。
ということはもはや温暖化時代に突入して、これはもう避けられないものと認識した方が良いのでしょうか。
結局、産業が石油をはじめとする化石燃料を消費している限り、個人レベルにてはどうにもならないのが現実でしょうし、仮に排出がSTOPしたところで、一旦走り始めた温暖化を逆戻りさせるのには何十年の歳月が必要。
何か抜本的対策があったらいいのですが。
二酸化炭素が問題ならばCO2をCとO2に分解してしまうということは出来ないものなのか。
実際に二酸化炭素増が水蒸気増につながり、それが温暖化をもたらすのであれば、世界各地の水蒸気を定期的に雨にしてしまう、とか。
北朝鮮もテポデンや短距離ミサイルを発射する代わりに、中国が北京オリンピック直前に披露してみせたみたいな、人工降雨ロケットでも飛ばせば、ちっとは評価も変ったでしょうに、ってそれも領空侵犯は領空侵犯だし、そういう名目で長距離ミサイルを開発されても困るか。ましてあの国がそんなことするわけないし。
と、とんでもないところに話が流れてしまいそうですが、そんな緊急の特効薬でもない限りはもはや「STOP・ザ・温暖化」どころではないのではないのでしょうか。
せめてもの提案。
ビルというもの屋上緑化はもちろん、壁面にも緑化工事を義務付けしてしまう。
管轄がもし、国土交通省なら、道路を作るお金をビルの緑化工事助成にでも使って頂けないものでしょうか。
温暖化ストップはともかくもここ近年続いているヒートアイランド現象の対策には少しでも役立つのではないでしょうか。
筆者は江戸時代の人々がいかにものをリサイクルしていたか、環境に優しかったかを書いておられるが、自ら述べておられるように今更、江戸時代に戻れるわけでも無し。
筆者は、
低炭素な街づくりを、
新しいビジネルモデルを、
もったいなくてもエコ製品へ買い替えを、
と解決策を模索される。
また、折りしも、昨日には温室ガスを2020年までに15%削減するという方針が首相より発表された。
しかしどうなのでしょう。
この筆者も政府も温暖化防止のための明確な答えを持ち合わせているわけではないのでしょう。
いくらビジネスモデルが少々変ったところで産業構造が少々変化したところで、個人個人の意識レベルが向上したところで、この温暖化のスピードを緩めることはあってもストップさせるわけじゃないでしょうし。
筆者も自ら述べておられるように慣性の法則ではないですが、STOPさせてもSTOPするまでに何十年かかるのですから。
では、どうすれば良いのか。
個人個人としてはもちろん出来る限りの「うちエコ」をしつつも、来たるべき温暖化社会、いやもう突入しているのでしたっけ。
その温暖化社会の中で生きて行く覚悟を持つべし、ということなんでしょうかねぇ。
最終的には。。