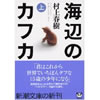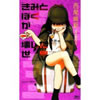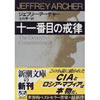この本、数あるジェフリー アーチャーの作品の中でもピカ一なのではないだろうか。
CIAのエージェントであるコナー・フィッツジェラルドに課せられた現役最後の役目、反米を売り物にする当選確実のコロンビア大統領候補の選挙期間中の暗殺。
この指令は、CIAのヘレン・デクスターという女性長官から発せられたもの。
この女性と副長官との会話などを読むと世の中に起こること全てが陰謀と謀略によるものではないか、とさえ思えてしまう。
自国の大統領でさえ、次の選挙まで間の短命な指導者。そんなものに追随するつもりなどさらさら無く、米国で最も権威、権力があって必要不可欠な存在は自分だと信じて疑わない。
アメリカの大統領が短命だって?でも任期は4年、再選時は現職有利な事が多いので2期8年間、その座に居る事が多いというのに。
それでも女性長官から言わせれば、大統領選挙は4年に一回でもその間に中間選挙があるので、2年に一回は大統領は国民に媚を売らねばならない。
それに比べてCIA長官の地位は選挙なんて無関係。
その気になれば20年でも30年でもその地位に踏みとどまれる。
4年~8年その地位に居る指導者でも「いずれは変わる」などと思われる程度なのだとしたら、日本の指導者は官僚からいったいどう思われているのだろう。
一年毎に交代する首相。1年に何人も入れ替わった農水大臣。
麻生政権が組閣してわずか5日。たったの5日で辞任してしまう国交省大臣。
各省庁の役人がそのリーダーシップに引っ張られて、なんてどう考えたって考えられない。
同じ9月。ほんの少し前に短命で去って行った大田農水大臣には職員から花束贈呈があったそうだが、この国交省大臣に関してはそんな事も行われなかっただろう。
まぁ、その花束代にしたって官僚が身銭を切っているとは思えない。どうせ税金なのだろうから、花束贈呈などという悪しき慣習も終わらせるに越したことはないが・・・。
話が少し横道に入ってしまったが、民意が選出した政治家の指導者に対する尊敬も信頼も命令服従の気持ちのかけらもない人間がそれぞれの省庁の実権を握っていることと、CIAの長官職に就いていることはある種共通するものがあるだろう。
もちろん官僚が暴走するよりもCIA長官が暴走する方がはるかに恐ろしいのだろうが・・・。
彼女の一言はありとあらゆる捏造を可能にする。
その気になればどんな人間のプライバシーだって知り得てしまう。
どんな政治家でも彼女がその気にばれば失脚させることなど容易いこと。
それまで存在した人間の生きた痕跡を消してしまうことだって行えてしまう。
これはもちろんフィクションだが、冒頭のコロンビアでも過去、選挙中、在任中を問わず、暗殺された指導者、国会議員などいくらでも居ただろう。
都度、麻薬を扱う非合法組織が仕組んだものとして片付けられた。
コロンビア以外でもそんな例はいくらでもあるだろう。
自国のケネディ暗殺にしてもそう。
このCIAの女性長官にかかればそんなことはいとも容易く行えてしまえそうなところがなんとも不気味である。
このCIAの女性長官に負けず劣らず、民主主義にて選出された指導者を小ばかにしているのが、ロシアの新大統領。
彼は就任した後に選挙は二度と行わないつもりでいる。
この本が出版されたのは1998年。まだエリツィン政権の時代だが、その先のプーチン政権の誕生を予見しているかの如くである。
両者とも「誇りある強いロシア」の再建を目指す。
小説に登場するゼリムスキーロシア新大統領は、スターリン、ブレジネフの再来と呼ばれることを喜ぶが、現実のプーチンはむしろソビエト誕生前の帝政ロシア時代の方を目指しているのかもしれない。
ソビエト時代に消えていたコサック兵なんかもプーチンの時代になって再来した。
秘密警察を再結成し、それが暗躍していることを世界に知らしめたのは2006年の女性ジャーナリストの暗殺だろう。
そして北京オリンピックの開幕と共に開始されたグルジア侵攻。
プーチンは任期8年で大統領の座を後任のメドヴェージェフへ引き渡したが、プーチンの傀儡政権とも呼ばれている。
生きている限りは政権TOPの座に、という物語のゼリムスキーと似ていないだろうか。
コロンビアの暗殺事件への関与を大統領から疑われたCIAの女性長官は、CIA内で最も有能なエージェントであるコナーの存在を消し去り、なきものするための画策を行うが・・・。
逆にCIAで最も有能なエージェントなだけにそんなに容易くなきものにされるのだろうか。
その舞台がひっきりなしに変わって行くので、読む側に若干の煩わしさはあるかもしれないが、逆にそれはそれで物語をテンポ良くさせてもいる。
とにかく最後の最後まで読みどころ満載な読み物なのだ。