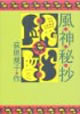変な国・日本の禁煙原理主義
変な国・日本の禁煙原理主義 山崎正和/養老孟司<文芸春秋10月号対談>
養老孟司先生と言えば以前良く読んでいたエッセイなを思い出す。
面識もないのに先生と呼ばわりは不遜かもしれない。
たとえ面識があっても学者というだけで先生などとは呼ばない主義である。
養老氏では無く、先生と呼びたくなるのには訳がある。
だいぶ前に読んだエッセイの中の一つに痔の治し方についての養老先生の独自にあみ出した方法が書いてあった。
当時、私の知人の中に何人か痔持ちがいて、痔というもの医者へ行って手術をして切っても切ってもまた数年後には再発して、医者へ行って切らなければならない、そんな病気なのだと言っていた。
それがなんと養老式の治し方を知人三人に紹介してみたところ、三人が三人共、医者へも行かず、手術もせずに完治したというのだ。
それを聞いて、私の中では養老氏は養老先生となり、尊敬の念すら抱く様になった。
何も痔の事だけではない。歯に衣を着せないそのエッセイでの語り口が好きなのだった。
この対談は煙草を推奨しようと言うものではない事はもちろんだが、「禁煙」というものへの世の中の行きすぎに警笛を鳴らしてだけの様にとらえられている向きもあるかもしれないが、私はそうは読まなかった。
本来個人の責務であり個人の自由であるべき「健康増進」というものにまで「健康増進法」などという法を作り、国が国民へ生き方についてまでの押し付けを行う。
また、それに対して誰も疑問を持たないこの国のあり様を憂いているのである。
健康増進法 第二条
(国民の責務)
「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない」
余計なおせっかいを通り越して責務だとはまるでファシズムの様だと対談では冒頭から過激な言葉が飛び交う。
かつて、日本のオフィスで禁煙というところは少なかった。
それが会議室となるともっと顕著で煙草の煙がもうもうとする中で会議をする、というのが当たり前だった様に思う。
アメリカの会社へ出向していた人がいて、帰国後
「アメリカの企業では一人でも私は煙草の煙が嫌いだという人がいたら、その会議室では煙草が吸えなくなるんだ」
というのを聞いた時には、皆がなんとまぁ理不尽な話だなぁ、などと言っていたものだ。
それが、あっと言う間に分煙化が進み、それが今やどうだろう会議室はもちろん、オフィス全てが禁煙は当たり前。わずかに喫煙室という小部屋があったものまで今やだんだんと無くなるか、戸外へ追いやられるか、という変わり様だ。
日本では、いや日本だけではないかもしれないが一つの事にヒートアップしてそれが過熱現象となる傾向が多々ある。
特に健康がからむとそのヒートアップは進む様だ。
一旦アスベストが悪いとなると、アスベストにヒートアップする。
かつては耐熱性にも耐薬品性にも優れ、耐久性も有り、電気に対する絶縁性も有る。
しかも安価であるという事で「夢の素材」とまで言われて普及していたアスベストがである。
食品に対してもやり玉にあげられた企業は数多い。
もちろん、うそ偽りを言っていた企業に責任があるのだろうが、中には何もそこまで・・と思える様なケースもあったが具体名は書かない。
「健康と安全」というお題目はなんと言っても強いのだ。
警察の交通課の言葉に「3Sの撲滅」というものがだいぶん以前からあった。
3Sとは「信号無視」「酒気帯び」「スピード違反」の三つだったと思う。
私は父と兄を交通事故で亡くしている。
両事故共に3Sは関係無かった。
事故があったのを聞いて病院に駆け付ける際にその病院には駐車場が無かった
ので、原動機付自転車(所謂原付)を使用した。
かなり安全運転に気を使ったつもりだったが、覆面パトに停められスピード違反の切符を切られた。
パトカーの警察官に私は言った。
「3Sと言いますがね、私の父親は信号無視も酒気帯びでも無いスピード違反もしていない、単なる運転の下手糞なオバさんに撥ねられたんですよ」
と言い、今からその病院に駆け付けるところだと述べてみたが、一応軽く同情はされたが切符はしっかりと切られた。
この3Sの中でもここ1~2年で急激にエスカレートして悪者になって来ているのが、酒気帯びである。
そりゃかなり酒気を帯びてのひどい事故が続いたからやむを得ないかもしれないが、本当にそこまでやる?というところまで来てしまっている様な気がしないでもない。
私共が住んでいる場所や仕事をしている場所は何分か待てば電車も来るし、タクシーだってそこらじゅうを走っているので構わないが、田舎の方は本当に成り立っているのだろうか。
電車は数時間に一本しかない。タクシーも走らない。ましてや運転代行屋さんなどいるわけもない。
そんな田舎はいくらでもある。
唯一の交通手段は車である。
知人のお通夜に行って「亡くなった人への供養だと思って」などと言われて酒を注がれて本当に拒めるものなのだろうか。
お正月のご挨拶に伺って、まぁ一献と差し出されたものを拒絶出来るのだろうか。
「このご時世ですから」と逃げ出せる人もいれば、拒みきれない人もいるだろう。
それがその地方で生きて行く生き方だとしたら尚更である。
だが、酒気帯びに対する罰則は都会も田舎も同じはず。
このバッシングは当分止みそうにない。
それは元々酒気帯びそのものは違反である、という過去からの決まりがある以上誰しも納得せざるを得ない。
ところが煙草はどうなんだ。
煙草を吸う事が犯罪か?
煙を吐く事は違反なのか?
大抵の場合はヒートアップはするが、またその熱がさめるのもあっと言う間である。
山崎・養老両先生も、煙草に対する嫌悪熱はいずれさがるだろうと見ていたフシがあるが両先生の意に反して、嫌悪熱は下がるどころか、ますますエスカレートして行ったのである。
ほんの十年前の映画ですら、煙草もくもくなんて当たり前だったのに、今や煙草吸いはまるで犯罪者の一歩手前の様な扱いである。
私も分煙には賛成。
歩き煙草もしない方がいいだろうと思うし、煙草のポイ捨てももちろん反対。
要はマナーの問題じゃないのか、と思うのだが、もはやマナーがどうであれ煙草はいけない、健康を害する、他人の健康をも害する、お前達煙草吸いは煙でもうもうとなった換気の悪い小部屋で肩身を狭くして吸うがいい、と言わんばかりの世の中。
両先生の主張を裏付ける訳ではないが、私も一日に煙草二箱を必ず吸うという九十何歳かのジイさんがピンピンしているのを現実として知っている。
九十数歳まで長生きした鄧小平だって単壺をに痰をペッペを吐きながら煙草を欠かさなかった事は有名だろう。
まぁ、そんなケースだけを取り出しても仕方がない事は承知している。
この対談を読んでいて思い出したのが喫煙者が世の中から迫害され、抹殺されて行く話を書いた筒井康孝の短編。
残念ながらタイトルは忘れた。
世の中そこまでは来ていないがかなりの部分でその短編の世界に近づきつつある。
この対談はかなり世間を賑わせたらしい事は最近知った。
禁煙の推進団体やら推進する学会などが、
「肺ガンの主な原因が喫煙ではないという根拠を示せ」
「受動喫煙には害がないという根拠をお示せ」
などと反論しているらしい事も聞いた。
なんか話が逆ではないのか。
両先生はその真逆の問いかけをしているのである。
・煙草が肺ガンの主な原因となるその根拠を示せ、と。
・受動喫煙に害がある事の根拠を示せ、と。
煙草についての検討会なるものでは、検討をする前に既に煙草が害悪である事が前提となっており禁煙推進者は喫煙擁護派には根拠資料すら開示しない事例もあげて憤慨されておられる。
両先生には笑止であろう。
養老先生は肺ガンの原因が煙草である事を医学的に証明出来たらノーベル賞ものだ、と以前から言っている。
根拠を示し、証明すべきはどちらなのかは自明の理である。
と、両先生を擁護する意見をここまで書いてしまったが良かったのだろうか。
ここは私個人の掲示板でもないのに。
まぁ、いいか。気にしない気にしない。
パイプを咥えていないシャーロックホームズなんて想像出来ないし、葉巻を咥えていないチャーチルも吉田茂も想像出来ない。
世の中良識ある言葉が往々にして葬られるものである。
この勢いだけはとまる気配が無い。
両先生の冗談でもあるまいが、いずれシャーロックホームズの挿絵のパイプだけがモザイクになって出版される日が来るかもしれない。
くわばら、くわばら。