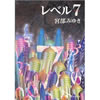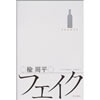鼠 (故城山三郎氏を偲んで)
3月22日、城山三郎氏が亡くなられました。
私にとって戦国時代から幕末、明治までの歴史の師が司馬遼太郎氏なら昭和史の師は城山三郎氏(以下敬称略)に他ならない。
歴史小説の司馬遼太郎と経済小説の城山三郎では畑が違うだろう、と思われる向きかもしれない。
司馬遼太郎が実在の人物をそのままの名前で書いていたのに対し、城山三郎の作品の大半は、実在のモデルはこの人だ、とほぼ誰でも判っていながらも架空の人物・企業として描いている。
書かれる方も同じ昭和のその時代を生きている人で、その企業も現存する以上、それは当然の配慮だろう。
いずれも学校で教えてもらえない日本の歴史、近代史、現代史を懇切丁寧に教えてもらったという意味では両者共自分にとっての師である事に違いは無い。
城山三郎の作品群は正に昭和そのもの、と言っても過言では無いだろう。
昭和の初期では『男子の本懐』で浜口雄幸、井上準之助を描き、戦中・敗戦まででは『大義の末』がある。
『大義の末』では軍神杉本中佐の『大義』「天皇のために身を捧げることが日本人の生き方である」という戦前の軍国少年のマニュアルの様な本に傾倒した学生の敗戦後のわだかまり、こだわりを描く。
著者そのものも『大義』を読んでいた、という事なのでたぶんに自身の思いを重ねていたのかもしれない。
敗戦の尻拭いの様な東京裁判で唯一文官でA級戦犯となった広田弘毅を描く『落日燃ゆ』。
その後の復興時は『価格破壊』が一代にして日本のトップスーパーを興した起業者を描いたかと思うと、これから高度成長へと向かう日本の牽引車となるべく海外の車に負けないものを、と取り組む自動車メーカーと下請け企業の悲哀を『勇者は語らず』で描き、『乗取り』はまさに昨今流行りのM&Aの先駆けの様な乗っ取り屋を描く。
そして時代背景は違うが、平成の今、丁度団塊の世代が定年退職に向かおうとするこの今の時期のためにある様な『毎日が日曜日』。
実在の人物を実名で描いているのは『鼠』、『男子の本懐』、『落日燃ゆ』・・とわずかであるが、これらの登場人物は寡黙を美とするところがあるのか、いずれも本人は本懐かもしれないが、はたから見れば不幸な結末を迎えている。
この追悼文のタイトルに『鼠』を持って来たのは、たまたま私が城山三郎を最初に読んだのが、この本だったから、という事になるだろうか。亡くなった、と聞いて一番先に読みたくなったのもやはりこの『鼠』だった。
『鼠』という作品はジャンルで言えば小説ではない。ドキュメンタリーそのものである。
そして大正時代が舞台である。
『鼠』を読むまで「鈴木商店」という会社の存在など全く知らなかった。
「鈴木商店」なんていう商店街の一店舗の様な名前の会社が一時は三井・三菱も凌ぐ日本のトップ商社だったなどと俄かに言われてもそんな事はなかなか信じがたいものがあるだろう。
「鈴木商店」は単なる一商社だった訳では無く、製鋼、金属精錬、造船、人絹、毛織、油脂工業、倉庫、海運、鉱山、樟脳、ビール、製糖、製粉、ゴム、・・・当時のありとあらゆる日本の主たる製造業を傘下とする大コングロマリットだったなどと言われて、素直に信じられるだろうか。
その時代の主力産業の大半を手掛けていた大企業なのだ。
「鈴木商店」を差配していたのは、金子直吉という大番頭。
質実剛健にして機を見るに敏。
自らの才覚に絶大な自信を持つ負けず嫌いの性格。
そして丁稚上がり故か、日曜日というものが無い。
歴史とはなんと残酷なのか。これほどの大企業でありながら、今、というよりこれが書かれた昭和の時代であっても「鈴木商店」の名は知られる事も無かったし、教科書で教えられる事もない。
歴史に潰された、もしくは埋められた存在と言ってもいいだろう。
大正の米騒動にて米を買い占めていたという理由で焼き討ちに合う。
当時のメディア、即ち大新聞だが、この「鈴木商店」をこれでもか、これでもか、というほどに悪徳商人として叩いている。
それに対して金子直吉は、「悪い事をしていない事はいずれ皆がわかってくれる」と新聞批判などには目もくれない。
当時の事を書いた史書にも尽く「鈴木商店」が買占めをした悪徳商人として書かれていながら、「鈴木商店」を知るわずかな生き残りの人達は「あぁ、なんていい会社だったんだろう」と語る。
そのギャップを疑問に感じた城山三郎の徹底した取材活動が始まる。
その史実の中で証言している人、一人一人に当時の事を取材していく。
証言者の口からは「なんせ、みんなが悪いって言うんだから、悪い事をやっていたんだろ」程度の事で、事実の「鈴木商店」の悪徳、背徳の事実は全く浮かび上がらない。
そしてそれらの偽りの証言を一つ残らず見事に覆し、大新聞の過剰な誤報についても論破し、「鈴木商店」の名誉を挽回させるのである。
「鈴木商店」は米の買占めをするどころか、当時高騰しく米を新聞が煽り立て、皆が買いだめをする最中、朝鮮米、外米を輸入して安い価格の米を流通させようと言う世論とは全く逆の事をしていた。
「鈴木商店」即ち金子直吉には米を買い占めて庶民の暮らしを食い物にしようなどと言う様なしみったれた気持ちはさらさら無く、それよりももっと大きなところへ目を向けて活動していた。
丁度この頃、英米が鉄輸出禁止令を発令。
日本に鉄が入って来ない事は日本にとって死活問題。
大統領へ直訴をしたためるが相手にされず。アメリカ政府代表として来日していたモリス代表に船舶を売りつけ、支払いは鉄にせよ、と交渉する。
まだまだ弱体日本が欧米相手に力を付けるという国家の事しか頭に無かった。
そんな「鈴木商店」をくる日もくる日も某大新聞はやり玉にあげ、悪徳商人呼ばわりをして罵る。
「鈴木商店焼き討ち」は新聞が火をつけた様なものである。あとは群集心理。
皆が「鈴木をつぶせ」とばかりに襲い掛かる。
マスコミ=新聞は当時の寺内内閣を叩くのが目的で「鈴木商店」は言わばおまけの様なものだったのかもしれないが、とんだ煽りである。
戦前日本には言論の自由の無い民主主義としては未開の国だったとのたまう向きもあるが、この一事を見てもわかる通り、言論の自由が無いどころの話では無い。
自由を通り越してすらいる。火の無い所に煙を立てて一企業を悪徳商人扱いにし、民衆を煽って暴徒化させる。そこまでの力を持っていたのである。
「焼き討ち」即倒産では無く、その後も「鈴木商店」は存続するのだが、金子直吉の銀行嫌いも手伝って、最後は解体を余儀なくされる。
「鈴木商店」は跡形も無く消え去った様で、実際には神戸製鋼、石川島播磨重工、サッポロビール、日商岩井、帝人、昭和シェル、豊年製油・・など日本を代表する企業にその血脈は連綿と流れ今も生き続けている。
しかし、この『鼠』というタイトルはどうなんだ。
いかにも米蔵の中で米でも齧っていそうなタイトルではないか。
このタイトル、金子直吉の白鼠という俳号からか。
「初夢や太閤秀吉奈翁(ナポレオン) 白鼠」
この俳句とも言えない様な句は、もちろん焼き討ち前のもの。
「落人の身を窄め行時雨哉」
鈴木商店解体後、住み慣れた家からも追われる時のもの。
『鼠』というタイトルはこの俳号からのものでは無い。
直吉は天下国家を望みながら本質において生涯勤労者だった。
「鼠」の様に走り廻らなければ生きて居れぬ人間だった。
城山三郎は取材に次ぐ取材の結果「鈴木商店」の名誉を挽回させたが、また一方の冷静な観察眼では「鼠」であるが故に金子直吉も「鈴木商店」を倒した一人だった、と捉えているのである。