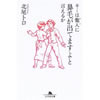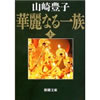キミは他人に鼻毛が出てますよと言えるか
こんなタイトルがついてんねんからおもろないわけないがな、って普通誰でも思てまうがな。
「幸せは歩いてこない だから歩いてゆくんだね」
「人生はワン・ツー・パンチ 汗かきべそかき歩こうよ」
365歩のマーチの引用と、汗かいてでもべそかいてでもええから小さな勇気を出してみようや、ちゅうイントロも悪くないがな。
そやそや。やらんと後悔して死んでまうぐらいやったらなんでも勇気出してやったらええがな。
そやけどな。そやけどやで。
・「電車で知らないオヤジに話しかける」
ええねんけどな。それそのものはそないに勇気もクソも無いやろ。
・「話しかけた後、一緒に飲みに行く」
これはあかんやろ。こんなもんポン引きに勘違いされるのんがオチやで。
まぁ、勇気のあるフリーライターには怖いもんも無いちゅう事か。
ところがどやねん。この人。
ほんまにフリーライターかいな。
人と話して取材してそれを記事にするのんを仕事にしてんのとちゃんかいな。
そのフリーライターにしては、なんちゅうアプローチの下手さやねん。
雑誌の企画やから何がなんでもちゅう気負いでもあんのんか。
それとも読み物としておもろいように過剰に表現してんのか。
まぁその両方があるとして、少々大袈裟に書いたとしてもほぼ実際に実行した事を書いてるんやろうな。
なんでもっと普通にいけへんねやろうな。
じーっとターゲットを観察してから、わざわざ他所が空いてんのに隣りに座っていきなり天気の話かいな。そら誰でも逃げ出すわな。
・「GWのお台場で孤独に見える青年に話しかける」
それもええんやけど、それがほんまにやらんと死んでから後悔する事なんかいな。
これも「電車の中でオヤジと」と全くおんなじや。
じーっと長い事観察して、待ち合わせやない事を確認してから近づいて行く。
ほんま、なんでこんな不審なんやろ。
誰が考えたってなんかの変な宗教の勧誘やんかいな。
しまいに一緒に観覧車に乗ろってな、一緒に来るやつ居るわけないがな。
・「公園で遊んでいる子供に話しかける」
これはさらにひどいで。
公園でじっくり子供を観察して、子供が遊んでいる所まで行って話しかけるってな、もうむちゃくちゃ危ないヤツやんかいな。
もうそれだけでも警察に通報されてもおかしないで。
それやのにこの人、子供が逃げ出すのんを「信じられん」とか「過剰反応」だとか言うとる。
なんかずれまくってんのんとちゃうんかいな。
フリーライターやったらいろんな記事も目にするやろうに。
その「過剰反応」をせーへんかった子供がどんだけ誘拐されたり殺されたりしてんねんな。
子供には寄って行ったらあかんがな。寄って来てもらわな。
・「激マズ蕎麦屋においしくない事を指摘する」
ってな。これのどこに勇気が居るんかさっぱりわからんわ。
「まずいでー」「しょっ辛いでー」って言うてあげるんは当たり前とちゃうんかいな。
そこに勇気ちゅうもんが介在せなあかん事の方が信じられんわ。
最近、近所に出来たラーメン屋がある。
そのラーメン屋からかん水のええ臭いして来たから、ふらふらーっと入って注文したら、出て来たラーメン麺がちゃんと湯だって無い。
ダシも今一や。
「せかっくええ臭い出してんのに、外のええ臭い負けしとんがな。麺もちゃんと湯だってないし。晩やから言うて手ぇ抜いてたら半年持たんと潰れてまうでー」
ってちゃんと言うてあげるのんが親切っちゅうもんや。
まぁ口に出して言わん時もあるけどな。
はるか昔の学生の頃のこっちゃ。
東京行って入った喫茶店でカレー頼んだ事がある。
見るからにまずそうなカレーやった。
テーブルの上にソースを探したけど見当たらんから、
「ちょっとソースもらえますか」って持って来たオバちゃんに言うたとたん、
「ウチはソースをかけなきゃ食べられない様なまずいカレーは出しておりません!!」
と来たがな。
なんちゅう居丈高な。
なんちゅう気ぐらいの高さや。
そらカレー専門店で言われんやったらまだしも。たかだか喫茶店カレーやろうが。
どないしたら喫茶店カレーぐらいでそないに高いプライド持てんねん。
一応ソース無しでトライしてみたけど案の定まずい。
結局、隣りの隣りのテーブルにあったソースをかけてみたけど、そんなもんではどうしようもないレベルやったから。
結局諦めた。
なんぼ喫茶店カレーでもこれは無いやろ。これやったらレトルト温めて出した方が千倍マシやで。
大阪やったらこの店焼き討ちに遭うてもおかしない。
おばちゃん、関西人はカレーにソースかけるもんと思てんのかもしれんけど、本場のインド料理の店でいろんなルーを仕込んでるもんにまでソースはかけんわいな。
ほんでもさすがに口に出して言うのはちょっと喧嘩売ってるみたいになってまうから、紙ナプキンかなんかに
「ソースかけても食べられないぐらいのまずさでした!」
ってしっかり書いてカレーの皿の下に置いて、勘定して店でたがな。
はたまた某高速道路のインターンチェンジで牛丼を頼んだ時のこっちゃ。
牛丼を頼んだんは俺だけとちゃうで。
俺のテーブルの友人も全員、隣りのテーブルでも他所の人が頼んどったわ。
順番に牛丼が運ばれて来て、順にふたを開けて食べ始める。
俺のところへ来た牛丼のふたを開けて、目ん玉飛びでそうになったで。
な、な、なんと巨大なゴキブリが・・・しかもしっかりと煮詰まった飴色のゴキブリがこのワシが目に入らぬか、とばかりにドデンと居るがな。
なんなんや、これ。
普通、肉盛りする時に気ぃ付くやろ。
当然の事ながら、交換してもらお、と思たんやが、廻りのみんなはもう食いはじめてる。
ようよう考えて見たら、たまたま俺の丼の中にゴキちゃんは居っただけで、鍋の中で煮詰められてる時には廻りのみんなの丼にも隣りの他所の人の丼にもゴキちゃんのエキスはしっかりと出てるはずや。
そない思たら、このゴキちゃんをふたへ移したら、みなと条件は同じや。
「この丼、ゴキブリおるでー」なんて大声で言うたら他所の客も皆、気分が悪うなるやろうし。
こういう所で働いてるのんは大概アルバイトの人や。そんなん言うてアルバイト困らせてもしゃーない。
という事でゴキちゃんにはふたへ移動してもらって、残さずきれいに食べたった。
一応、その店の今後の事も考えて、
「ゴキブリのええダシでとったわ」
ってメモをふたの下に入れておいて店員が片付ける時にゴキちゃんとメモはしっかり目に入る様にして、勘定して出た。
まぁ直接口に出して言わん事もたまにはあるかな。
・「友人に貸した小銭」の話はちょっとせこ過ぎて読んでられん。
いずれにしたって、このライターさん後悔せんようにやってるはずやのに。
もう二度とせんとこ、ちゅう感じで終ってるで。
「それでも私の中で何かが変わった」ってちょっとは世間が見えて来たんかいな。
ここで言うてはる小さな勇気って世にも有名な大阪のオバはんにしてみたら勇気でもなんでものうて、それこそ日常なんとちゃうやろか。
ちゅう事でこのへんで終わりにしよか、と思いつつもこのままやったらこの作者の事いっこも誉めてないがな。そら、まずいやろ。
・「鼻毛が出てますよと言えるか」
でいこか。
これはちょっと微妙やな。
どのぐらいで鼻毛ちゅうものは出てる事になるんか。
何本ぐらいやったら出てる事になるんか。
社会の窓が開いてる相手への伝え方はそれなりに心得てるつもりやけど、こっちの鼻毛の方は、その基準がようわからん。
しかも相手は初対面やろ。
無理やな。俺は言わんやろうな。
言われたらどうか。お互いの立場も関係して来るかもしれんけど、
たぶん「それがどないしてん」って返してまうんちゃうか。
立派や。ライターさん、よう言うた。良かった。ようやくこれで誉めて終れる。
最後に一言。
大阪のオバちゃんやったら、前後関係全く関係無しで言うてまうんやろうな。
「兄ちゃん、鼻から花咲いてんで」って。