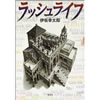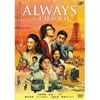ラッシュライフ
伊坂幸太郎続きになってしまいました。
「重力ピエロ」の感想はちょっと手厳しすぎますよね。
クロマニヨン人とネアンデルタール人の芸術論は壁の落書きを消す仕事をしているハルの事を語るには必要だったのでしょうし、ピカソの死んだ日に生まれたハルにはピカソの話は欠かせない。ガンジーを尊敬するという生き方を語る上でもガンジーの話はあった方がいいでしょう。
それぞれの必然があって登場させているのでしょう。
バタイユを語っていた探偵ならぬ泥棒さん、このラッシュライフにも登場しているんですよ。
それより何より、文化と書いてハニカミというルビを振る云々の太宰の文章がこのラッシュライフに出て来た時にはさすがに驚きました。
なんと言う偶然!
さてこのラッシュライフという話、かなり凝った作りであります。
異なる登場人物が異なるシチュエーションで登場して来るケースは本や映画では良くある事なのですが、それらがどこかで合体して行きますよね。
それまでの間、読者はかなりじれったい思いをするわけですが、この本の場合、そのじれったさをなかなか解消してくれないんですよ。
本の半ばまで来てもまだ掠る程度。
「重力ピエロ」で登場した泥棒さんは、後々盗まれた人が自分に恨みを持った人間の犯行ではない、と安心させるためにキチンといくらどこから持って行きました、というメモを置いて帰る、という几帳面な泥棒さん、しかも百万の札束がいくつかあってもその中のニ、三十万を抜くだけに留めるという謙虚な泥棒さん。
通常、百万の札束がいくつかあった中のニ、三十万ならメモなど残さなくてもまさか泥棒なんてと、思い違いか何かだろうで、済んでしまうでしょうに。
実際にそうやって、同じ所へ繰り返して入る手口も実際にあるのでは・・と思ってしまいます。
その泥棒さんの話が出たかと思うと、場面は変わってリストラされて失業者となり連続40回も就職に失敗した男の話、はたまた精神科医の女医と現役のサッカー選手が共謀して殺人を企てている話、かつて連続犯罪の謎を解き明かした事で一躍名探偵と話題になった人とそれを神と崇める新興宗教の信者の様な人達の話、金で買えないものは無いと考える大金持ちの画商・・・
それぞれが最初は全く繋がっていない。唯一仙台という場所だけが繋がっているものが、いつ繋がんだろう、いつ繋がんだろうと思っているうちにそれぞれの話が進行して行き、最終的には全てが繋がるのは一番最後。
しかも個々の話は時間差があって、ある人の話は別の人の話の数日前に有った事を引き継いでいたり、またこっちの人の話はその数日後を引き継いでいたりする。
そしてちゃんと全部繋がっているのです。
なんともはや凝った作りなのです。
途中までのじれったさはさておき、充分に楽しませてもらいました。
こういうのもやはりミステリーと言うのですかねぇ。