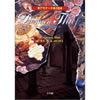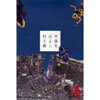村上龍さんと言えば「愛と幻想のファシズム」が以前、このコーナーにて取り上げられているが、そこからいきなり「半島を出よ」までとんでしまうのは惜しい気がする。
あの名作「五分後の世界」までも飛ばしてしまうなんて。だが、同じ感想を書くにしても新しいものから書くのが新鮮というものだろう。
とは言え、「愛と幻想のファシズム」に関しても何らまともな感想が述べられている訳では無い。手っ取り早く言えば、「読めばわかる」という事をたらたらと述べているにすぎない。
「半島を出よ」は近未来小説である。
近未来も近未来、ほんの5~6年後の世界なのだ。しかもかなりリアルなシロモノだ。
本編の描く未来は2011年。しかもわずか10日間あまりの出来事である。
北朝鮮の反乱軍と日本政府、マスコミ、そして社会からドロップアウトした若者達が話の主役なのではあるが、そこまでに至る経緯、時代背景の描き方、その演出には恐れ入る。
冒頭に出て来る、リョッコウと呼ばれる元公園のホームレス居住区の風景描写なぞはその典型。
「東大・京大・一橋大卒業証明書有りで三万円」と書かれた精子バンクのパンフレット。
穴を掘ってダンボールで囲っただけの便所。ダンボールの下から女の尻が見えていても誰も気にもとめない。
ヤクザがNPOとなってホームレスエリアの利権を漁る。
日本や各国の動きについても見逃せない。
2006年には団塊の世代の公務員退職金未払がはじまり、地方債と財投債が暴落。
金利が暴騰し、インフレと不況が日本を襲い、2007年にATMストップ。
政府は財政破綻し、預金封鎖に踏みったのだ。
消費税は上がり続け17.5%に。
日本はアメリカからもヨーロッパ、ロシア、中国、韓国からも孤立し、日米安保も解消寸前に。失業者の増加。増え続けるホームレス。
国民は導入された住基ネットの住民票コードで管理され、個人情報の全てはこの住民票コードにぶら下がっている。
アメリカも世界の警察である事を止め、イスラエルはパレスチナの独立を認め・・・。
近未来でありながら、直近の歴史を読んでいるかの如くである。
北朝鮮のこの作戦のヒントは、第二次世界大戦時のヒットラーの作戦だった。
亡命ユダヤ人に紛れた特殊戦部隊の一個中隊が客船でニューヨークに上陸し、マンハッタンを占拠する。
その部隊は、ナチスから逃れて来た反乱軍だと主張し、ヒットラーもそれを認める。
その反乱軍と名乗る一隊に市民は人質に取られ、アメリカはパニックに・・。
まさか、なのである。
そのまさかを北朝鮮が福岡を舞台として繰り広げる。
北朝鮮は日本にたった9人の北朝鮮のコマンドを乗り込ませ、福岡ドームを乗っ取る。
政府が全く無策のまま、後続部隊が到着し、たった500人の北朝鮮部隊は、無抵抗の国に乗り込み全く無傷のままで人口100万都市を手に入れ統治する。
駐留部隊は北朝鮮の反乱軍と名乗っているので、北朝鮮による侵攻とはならず、アメリカ、中国、韓国、国連は静観。
500人のみならず、後続の12万人の反乱軍が北朝鮮を出航しようとしている中、日本政府のやった事と言えば、九州の封鎖と北朝鮮への非難。
ほんの5~6年後の日本を描き、金日成、金正日、北朝鮮・・と実名をあげて書いている。
内容が内容である。しかもそのリアルさとあまりの生々しさ故に、私は村上龍さんの身辺に何か起こりはしないか、と読みながら心配をしてしまった。
だが、もう出版されて広く読まれているのである。毎日出版文化賞も受賞した。
寧ろ書き上げている時の方が遥かに恐ろしい。よほどの緊張感の中で書き上げたのでは無いだろうか。
下巻の巻末に参考文献が記されているが、その膨大な量も去ることながらその分野のなんと幅広い事か。
北朝鮮関連が最も多い。北鮮関連では、脱北者の関連文献から金正日回顧録の類、北朝鮮の童話本に至るまで、北朝鮮と名の付く本は全て漁ったのではないかと思えるほどだ。
他には、国際法関連、安保関連、特殊部隊、兵器、武器、火薬、爆薬関連、住基ネット関連、預金封鎖の関連、エシュロン関連、建築設備関連、虫、爬虫類関連、医学関連書籍・・・そして膨大な映像資料。
村上龍さんの書いている事で一貫しているのは、二者択一しか選択肢が無いのにそれを曖昧なものにしてしまう者達への批判、非難、軽蔑である。
それが、プライドという四文字に表現される事もあれば、裏返しに自信喪失という形でも表現される。
政府しかりマスコミしかり、何より日本人そのものしかりなのである。
そしてその曖昧模糊に対峙するのは、以前は若い女性が主役だった様に思う。
応えの出せない男共に対して、失うものの無い若い女性の方が考え方がシンプルで、迷い無く応えを出して行く。
社会からドロップアウトした少年達がその役割を果たし始めるのは、「希望の国のエクソダス」の前後からだろうか。
この本の中のもう一つの主役達である少年達も「共生虫」あたりから登場し始める、世の中、社会、大人・・というものに溶け込めない少年達に類似したものを感じる。
未読の方の為にも、最後は書かないが、この本の中では社会から、大人から不要とされた少年達が活躍する。
この本に書かれている事は荒唐無稽と読む人も入れば、近未来小説というカテゴリの一つに納めてしまう向きもあろう。
確かに近未来の架空の話ではあるが、ここに登場する人々が陥った様な「これまでに実感の無い現実」を目の前にした時の日本政府、マスコミ、日本人の姿は現実そのものなのである。