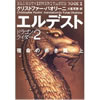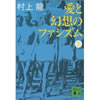世界不思議発見 南インド大紀行
世界不思議発見 南インド大紀行
ここはスタッフが読んだ読み物を元にあれこれ好き勝手な事を書くコーナーであるが、今回はテレビの番組で面白い光景を見たのでそれを書いてみたいと思う。
南インドにはまだジャイナ教と呼ばれる宗教が残っている。
ジャイナ教は生き物を一切、殺さない。
水を使用する際にもわざわざ布で濾してからその水を使用する。
それは水に含まれる混在物を取り除いてきれいな水を使用しようという目的かと思えばさにあらず。水の中に混ざってしまった生き物を間違って殺してしまわない為だという。
徹底している。
また、当然ベジタリアンであるにも関わらず、根菜の食を禁じている。
仏教にも不殺生の考え方はあるが、根菜の食までを禁じてしまうなどという話は聞いた事が無い。根菜、要は大根、人参、玉葱、芋などの根っこの部分の野菜、これらを収穫する際に小さな虫を殺してしまう可能性があるという理由で、その食を禁じてしまっている。究極の不殺生宗教ではないだろうか。
エルデストに登場するエルフもベジタリアンで、不殺生であるがさすがにジャイナ教には顔負けだろう。
ベジタリアンの食事から玉葱、芋類、大根、人参などが無くなったらどれだけ味気ない食事になるのだろうか。豆類だけで果たして満足出来るものなのだろうか。
ジャイナ教の信者はその聖地シュラヴァナベルゴーラにある世界最大の仏像、ゴーマテーシュワラを祭っている。奈良の大仏さんよりはるかに大きいし新しく見えるが、実際には1000年以上前に建立されたものだと言われている。
その巨大なゴーマテーシュワラ像はなんと驚く事に全裸なのだ。衣服を一切纏っていない。それはジャイナ教の中の一派が物を所有する事を禁じているところから、衣服ですら所有しないという思想がゴーマテーシュワラ像に表れているのだ。
その聖地で12年に一度行われるというマハマスタカゼェーカ祭という祭りの映像が流れていた。ゴーマテーシュワラ像に貴重であるはずの牛乳などの飲料を頭から全身が真っ白になるほどにぶっかけてしまうのだ。かなりの贅沢な行事だろう。
そんな贅沢をしてでも惜しくないというほどに信心が深いという事であろうか。
貴重な発見を見せてもらった。